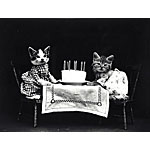もともと肉食の猫ですが、肉以外にも手作りで餌を作る時に取り入れると良い食材があります。 ですが、どの場合も過度に摂り過ぎると体調を壊してしまいかねません。 手作りで健康になる餌を猫の様子を見ながらじっくり進めたいですね。
手作りで野菜を取り入れた餌作り
野菜に含まれるセルロースを消化でいないため、たくさん摂り過ぎると胃腸に負担がかかり下痢や便秘の原因になります。 野菜は栄養豊富なものが多く、適量なら体に良い食材です。 食べやすいように刻んだりペースト状にしたりと食べ方を工夫をすると負担を減らせます。 手作りで餌を作ることが初心者の方は、野菜の中でも、アクの少ない白菜やレタスを使うとトラブルが少なく良いと思います。
キャベツは食物繊維が豊富でみじかな食材ですが、猫にとっては消化しにくい食材と言えます。与える量に注意しましょう。 また、猫はよく噛まないで食べるのでキャベツの葉をそのまま与えるのも良くありません。お湯でゆがいて柔らかくするか、細かく刻んで与えてください。
トマトは栄養満点でしかもカロリーが低めなので食べさせても大丈夫です。 ただし、十分に熟れたトマトを選んでください。 酸味が強いものはあげないほうが良いと思います。 餌を手作りするのに使うときは赤い実の部分だけを適量だけ使うとようにするといいと思います。
果物好きな猫もいるそうですが食べてもいいの?
リンゴをおいしそうに食べる猫や、バナナを食べる猫の動画をみたことがあります。 猫は野菜や果物などの食物繊維を消化するのはあまり上手ではないので、消化不良や下痢の原因になることがあります。 りんごやバナナには、ビタミンCやカリウムやミネラルなどがたくさん入っています。 とても栄養があってよいのですが、摂り過ぎると結石の恐れも出たり、高齢の猫には腎臓に負担がかかりますので注意が必要です。 猫の餌を手作りして食べさせる時は細かく刻んだりジュースにしたりと工夫して少量だけあげてください。
レバーは食べすぎに注意が必要な食材
レバーはビタミンAがったっぷり含まれていて、手作りで餌を与える際の食材としてぜひ取り入れたいもののひとつです。 ですが、そんなレバーは食べてはいけない危険な食材としても紹介されています。 レバーは体に良いのですが、食べすぎるとビタミンA過剰症になるので少量づつ食べさせるように注意が必要です。
卵は生ではダメ!調理法に注意して
卵には良質なたんぱく質が含まれていますので、手作りの餌作りにはうまく利用すると良い食材です。 ただし、生の卵を食べると皮膚炎や結膜炎といった症状が出る場合がありますので必ず加熱調理する必要があります。 ゆで卵を細かく潰したり、スクランブルエッグにして食べさせてあげると良いと思います。
食べてはいけない食材には注意が必要ですが、ダメだと諦めてしまわずに、その調理方法や量を加減すれば手作りで作る餌のレシピの幅が広がります。 大切な猫ちゃんに健康で充実した食生活を送らせてあげられたら最高ですね。